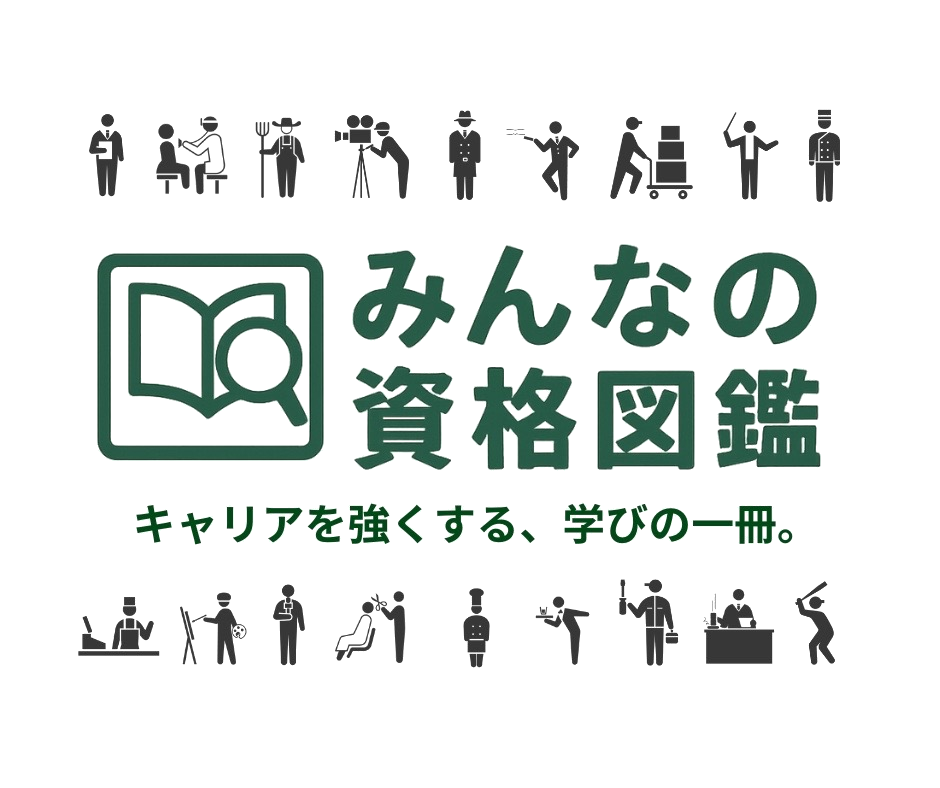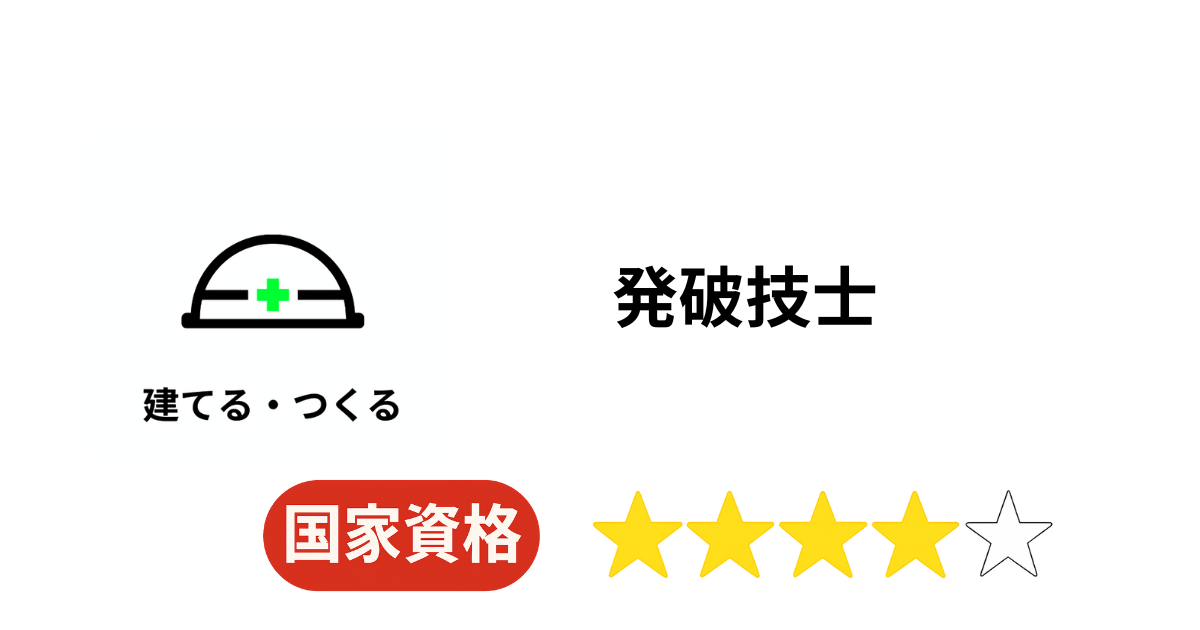発破技士(はっぱぎし)とは?
発破技士は、「火薬類取締法」に基づく国家資格で、火薬や爆薬を用いた発破作業を安全に行うために必要です。 発破とは、建設工事やトンネル掘削、鉱山開発、ダム建設などで岩盤や土砂を爆薬の力で破砕・掘削する作業を指します。これらの作業は強大な爆発力を扱うため、事故が起きれば作業員や周囲の人々、さらには社会インフラ全体に甚大な被害を与える可能性があり、厳格な安全管理が不可欠です。そのため、発破作業を行う際には必ず発破技士の資格が必要とされています。
この資格は火薬類取締法に基づいて設けられており、爆薬の取り扱いから発破の設計・施工、安全確認に至るまで、幅広い専門知識を学びます。特に、爆薬の種類や性能、火薬の保存・管理方法、雷管や導火線といった発破器材の正しい使用法、さらに気象条件や地質条件を踏まえた発破計画の立案など、高度な知識と判断力が求められます。発破は工事全体の進捗や品質、安全性を大きく左右するため、現場における責任も極めて重大です。
発破技士の役割は単に火薬を爆発させることではありません。現場では施工計画に基づいて発破の位置や規模を設計し、作業員に安全な退避を指示しながら作業を実施します。さらに、近隣の建物や交通、環境への影響を考慮し、騒音や振動を最小限に抑える工夫も必要です。発破作業は精密さが求められ、爆発の威力を制御する技術が現場の信頼性を左右します。そのため、発破技士は安全と効率を両立させるための中心的存在といえます。
また、発破技士は資格取得後も継続的な学習が求められる職種です。新しい爆薬技術や施工方法、環境基準の変化などに対応しながら、最新の知識と実務経験を積む必要があります。社会基盤の整備やエネルギー開発、鉱山資源の活用など、発破技士の活動範囲は幅広く、日本のインフラと産業を支える重要な役割を果たしています。
発破技士の試験概要
| 根拠法令 |
「火薬類取締法」に基づく国家資格です。 火薬類を使った発破(爆破作業)を安全に実施するために必要な資格として位置づけられています。 |
|---|---|
| 所管官庁 | 経済産業省(試験実施:都道府県知事または委託機関)。 |
| 受験資格 |
18歳以上であれば受験可能。 学歴や実務経験の制限はありません。 |
| 試験内容 |
・火薬類の種類、性質、保存・取扱方法 ・電気雷管、導火線、点火器などの構造と使用法 ・発破計画の立て方、安全距離、装薬量の算定 ・破砕・掘削・切羽処理など発破施工技術 ・火薬類取締法、労働安全衛生法など関連法令 ・事故防止、危険予知、現場での責任と安全管理 |
| 試験形式 |
【学科試験】筆記(四肢択一式+記述あり) ※発破実務の理解が要求されるため、理論的な問題が多いのが特徴。 |
| 特徴 |
山岳工事・トンネル工事・採石場・鉱山など、重機だけでは困難な掘削作業で必要とされる専門資格。 国家資格の中では安全管理の責任が重く、現場での信頼度が非常に高い専門職です。 |
発破技士Q&A
Q1. 発破技士はどんな仕事をする?
火薬類を使って岩盤・地盤を破砕し、掘削を効率化する専門職です。
安全に爆発を制御し、周囲に被害を出さないための計画と実行が主な役割です。
Q2. 危険性は高い?
火薬類を扱うためリスクはあります。
その分、法律で厳しく管理され、資格者しか作業できない仕組みになっています。
Q3. どんな現場で活躍できる?
・トンネル工事
・道路・ダム・鉄道の建設
・採石場・砕石場
・鉱山
重機だけでは掘れない現場で活躍します。
Q4. 理系じゃないと難しい?
力学や爆発理論の基礎が出題されますが、参考書で十分に学習できます。
現場経験があると理解が早いですが、未経験でも合格は可能です。
Q5. 一緒に取ると扱いやすくなる資格は?
・火薬類保安責任者(乙種・甲種)
・安全衛生責任者教育
・ずい道等掘削作業主任者
・採石のための作業主任者
発破関連の仕事ではセットで持っておくと評価が高まります。
発破技士が必要な職業/あると有利な職業
必ず必要な職業
あると有利な職業
公式情報/出典
- 経済産業省「火薬類取締法」関連資料
- 発破技士試験関連案内
難易度: ⭐️⭐️⭐️⭐️ (難易度4)
※高度な専門知識と責任が求められるため、難易度は高め。