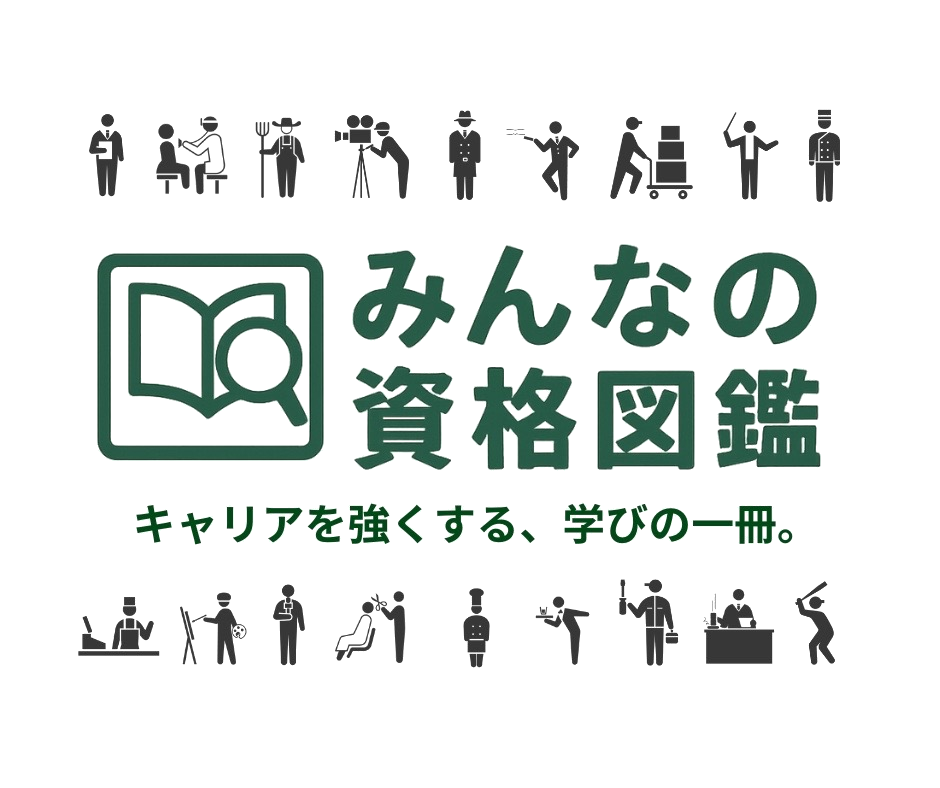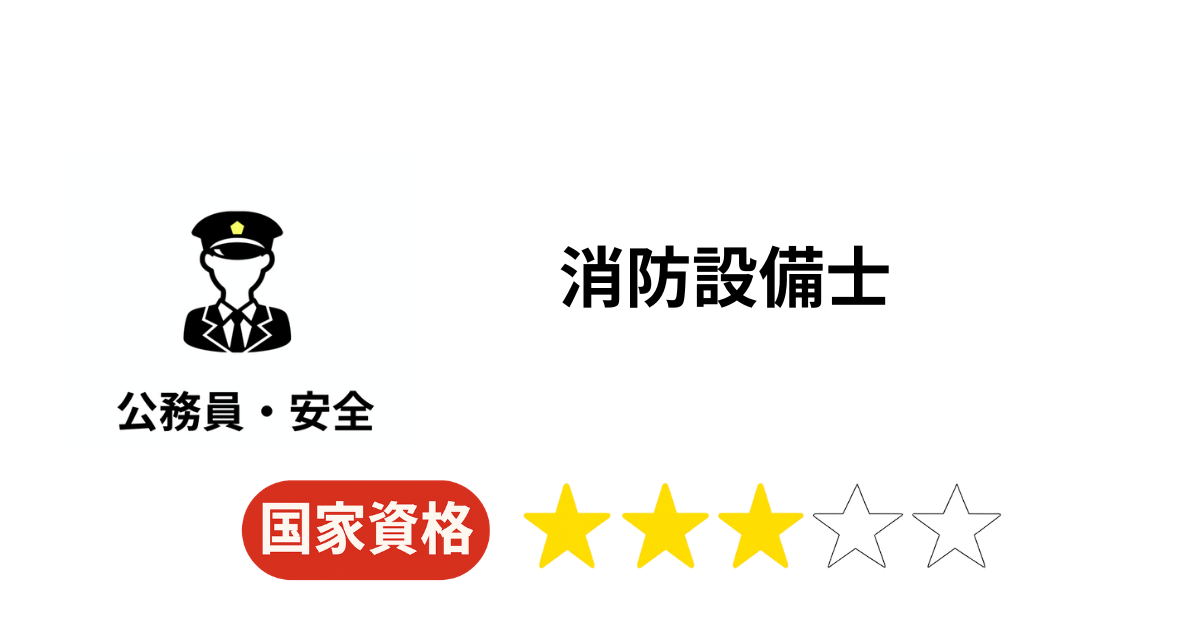公務員・安全を守る仕事
消防設備士(しょうぼうせつびし)とは?
消防設備士は、消防法に基づく国家資格で、ビルや商業施設、工場などに設置される消火設備・警報設備・避難設備の点検や工事を行うために必要な資格です。 消防設備の設置や整備には有資格者の関与が法律で義務付けられており、防火・防災の専門家として建築物の安全を守ります。 資格は「甲種(1〜5類)」と「乙種(1〜7類)」に分かれ、扱える設備の範囲や工事・点検の可否が異なります。
消防設備士は、ビルメンテナンス業界や建設業界で需要が高く、特に大規模施設や病院、学校などの防火安全を支える上で欠かせない存在です。社会的責任が大きく、将来的にも安定した活躍が期待できます。
消防設備士を取るために必要なこと・受験概要
| 根拠法令 | 消防法(第17条の6〜17条の12) |
|---|---|
| 所管官庁 | 総務省消防庁 |
| 実施団体 | 一般財団法人 消防試験研究センター |
| 受験資格 |
・甲種:関連学科の履修または実務経験など条件あり ・乙種:基本的に誰でも受験可能(制限なし) |
| 資格区分 |
【甲種(A〜F類)】 【乙種(1〜7類)】 消火設備、警報設備、避難設備など、設備ごとに細かく分かれる。 |
| 試験内容 |
・消防関係法令 ・構造・機能・点検整備 ・実技試験(鑑別・製図)※区分により異なる |
| 試験方式 |
筆記試験+実技試験(鑑別) ※一部区分は製図あり |
| 合格率 |
甲種:15〜30%前後 乙種:30〜50%前後 ※製図がある区分は合格率が低め |
| 免状交付 | 各都道府県知事 |
| 特徴 |
ビル・商業施設・工場などで必須の資格。 点検業務・工事業務のいずれでも活かせるため、需要が安定している。 消防設備業界では“持っていて当たり前”レベルで評価される。 |
消防設備士試験の勉強方法Q&A
- Q1. 消防設備士はどの区分から取るのが一般的?
-
最も受験者が多いのは「乙6(消火器)」と「乙4(自動火災報知設備)」。
特に仕事で使う場合は乙4が定番。 - Q2. 文系でも受かる?
-
十分に受かる。
法令は暗記中心、鑑別はパターン学習で対応できる。
製図がある区分は少し練習が必要だが、繰り返せば身につく。 - Q3. 勉強時間の目安は?
-
・乙種:20〜40時間程度
・甲種:80〜150時間程度
実技(鑑別)の仕組みを押さえれば短期間でも合格しやすい。 - Q4. 最短で受かるには何をすべき?
- とにかく「鑑別問題の反復」。 図記号・配線図・機器の特徴を覚えれば、一気に取りやすくなる。
- Q5. 消防法令の覚え方は?
-
細かく覚えようとすると挫折しがち。
「この設備はどこに必要なのか」という“目的”から逆算すると覚えやすい。 - Q6. 製図がある区分は難しい?
-
最初はとっつきにくいが、課題パターンはほぼ固定。
線の引き方・記号の位置を反復すれば確実に慣れる。 - Q7. どんな現場で役に立つ?
-
・消防設備点検業
・電気工事会社
・ビル管理会社(ビルメン)
・設備会社、工場の保全部門 など、安定した需要があり“資格手当”も付きやすい。
消防設備士が必要な職業/あると有利な職業
必ず必要な職業
- 消防設備技士:消防設備の工事・点検業務に必須
あると有利な職業
- ビルメンテナンススタッフ:建築物の消防設備点検で評価される
公式情報/出典
- 総務省 消防庁「消防設備士制度概要」
- 消防試験研究センター「消防設備士試験案内(令和6年度)」
- 消防試験研究センター「消防設備士試験結果(令和5年度)」
難易度: ⭐️⭐️⭐️ (難易度3)
※難易度は合格率・学習時間・試験範囲をもとに当サイト独自に評価しています。