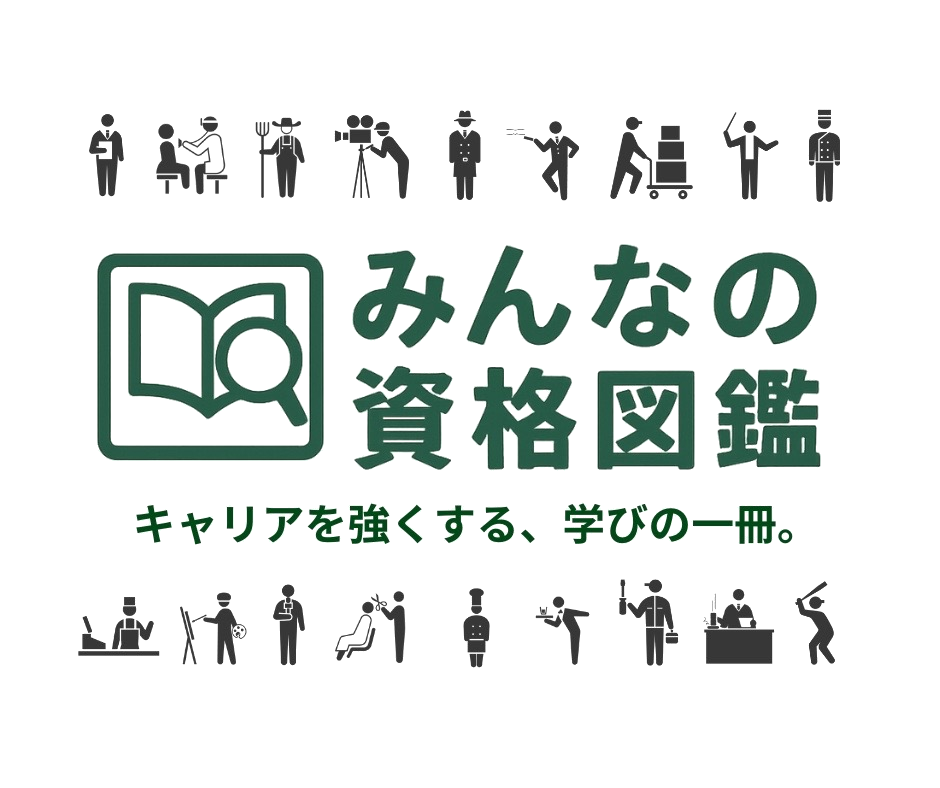環境とエネルギーの仕事
放射線取扱主任者(ほうしゃせんとりあつかいしゅにんしゃ)とは?
放射線取扱主任者は、放射線障害防止法に基づき、放射性同位元素や放射線発生装置を取り扱う施設において、安全管理を行うために必置とされる国家資格です。 研究機関、医療機関、原子力関連施設などで、放射線の使用計画・管理・教育を行い、法令遵守を確保する重要な役割を担います。
放射線取扱主任者は第一種から第三種まで区分があり、第一種はすべての放射線源を扱える最上位資格、第二種は中規模、第三種は小規模施設に限定されます。取得には理工系の知識と国家試験合格が必要で、医療現場のX線や放射線治療、原子力施設での管理、工業用の非破壊検査など活躍分野は多岐にわたります。放射線の安全利用を確保するため、社会にとって不可欠な資格といえます。
放射線取扱主任者の試験概要
| 根拠法令 |
放射線障害防止法に基づく国家資格。 放射線を扱う事業所で、安全管理を行うための専門資格です。 |
|---|---|
| 所管官庁 | 原子力規制委員会(試験実施:原子力安全技術センター)。 |
| 受験資格 |
学歴や実務経験による制限はありません。 ただし、第1種は出題範囲が広く、物理・化学の基礎が役立つ場面があります。 |
| 試験日程 | 年1回(例年8〜9月頃に実施)。 |
| 試験形式 |
■ 筆記試験(多肢選択式) ■ 科目合格制度あり(合格科目は一定期間有効) ※科目合格を積み重ねて取得する人も多い資格です。 |
| 試験科目 |
・放射線に関する物理学 ・放射線の生体影響 ・放射線の計測と防護 ・放射線施設の管理、関連法令 など |
| 合格率 |
年度によって大きく変動しますが、全体としては控えめな水準です。 科目合格制度を活用しながら、段階的に狙う人が多いです。 |
| 難易度 |
第1種はより広く深い知識が必要。 第2種は医療・工業分野で多く利用され、初学者でも取り組みやすい内容です。 |
放射線取扱主任者 Q&A
- Q1. 放射線取扱主任者はどんな職場で役立つ資格?
-
病院、研究機関、工場など、放射線を扱う場面で安全管理を担う仕事に生かせます。
日常的な点検や記録管理など、裏方として頼られるポジションが増える印象です。 - Q2. 第1種と第2種の違いは?
-
第1種は取り扱える放射線源の範囲が広く、専門性も高めです。
第2種は医療・工業など、より身近な現場で必要とされるケースが多いです。
自分の働きたい分野に合わせて選ぶと無理がありません。 - Q3. 勉強方法はどんなやり方が多い?
-
科目ごとに積み上げられる試験なので、1科目ずつ丁寧に進める人が多いです。
物理や計測の単元は、図やイメージで理解していくと負担が少ないかもしれません。 - Q4. 初めてでも合格は目指せますか?
-
はじめは専門用語が多く感じますが、ゆっくり慣れていけば十分対応できます。
試験範囲は決まっているので、過去問を続けるほど理解が深まりやすいです。 - Q5. 合格するとどんなメリットがありますか?
-
・医療・研究・工業など幅広い分野で安全管理の知識が評価される
・資格手当や役職につながる職場もある
・放射線を扱う現場で責任ある業務に関われる
安全面を支える立場として、着実に力を発揮できる資格です。
放射線取扱主任者が必要な職業/あると有利な職業
必ず必要な職業
- 放射線技師:放射線を扱う医療機関などで必置
あると有利な職業
- 研究者:研究炉や原子力施設で必須スキルとして評価
公式情報/出典
- 原子力規制委員会「放射線取扱主任者試験案内」
- 原子力規制委員会「試験結果(令和5年度)」
難易度: ⭐️⭐️⭐️⭐️ (難易度4)
※難易度は合格率・実務要件・試験範囲をもとに当サイト独自に評価しています。