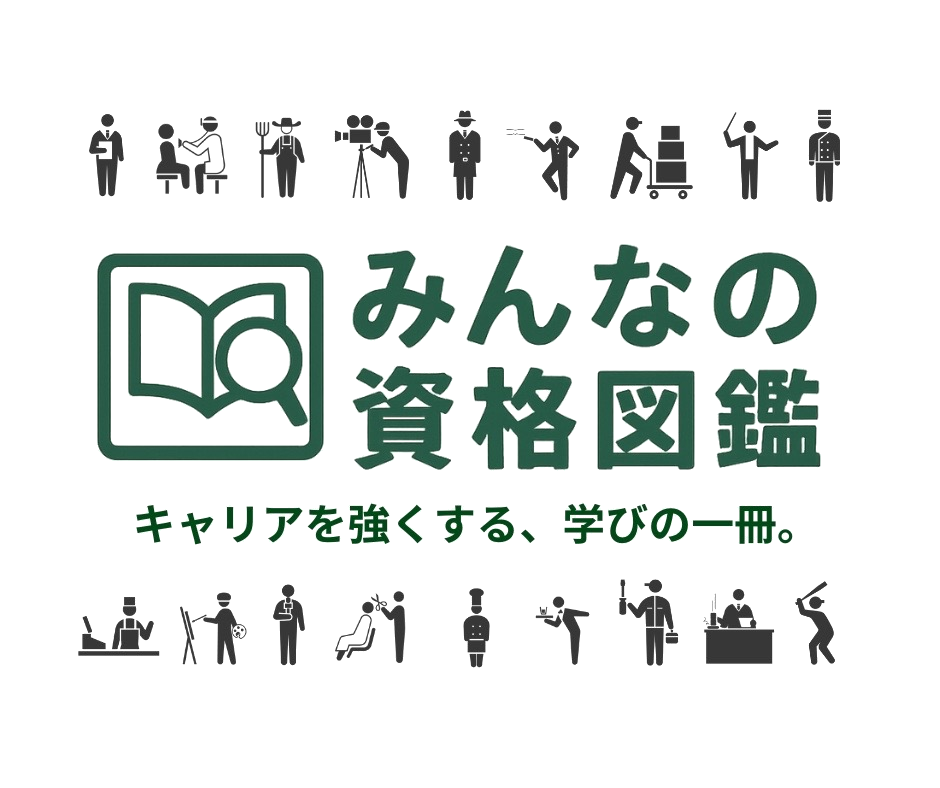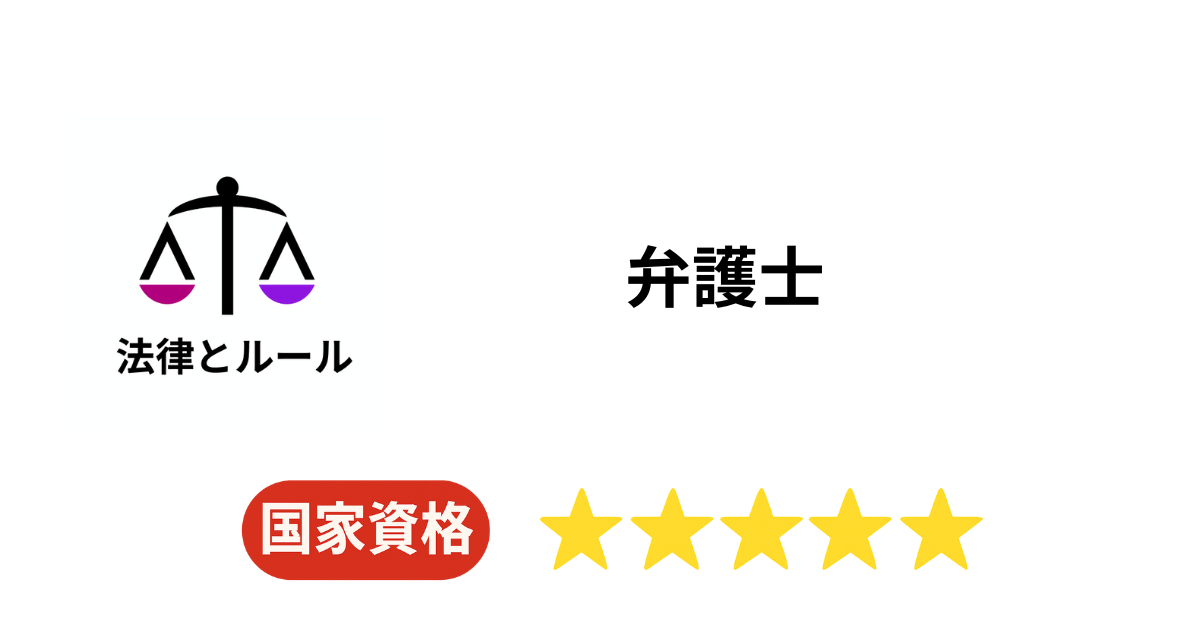法律とルールを守る仕事
弁護士(べんごし)とは?
弁護士は、司法試験に合格し、司法修習を修了した上で日本弁護士連合会に登録することで資格を得られる国家資格です。 憲法・民法・刑法をはじめとする法律に基づき、依頼人の代理人として交渉や訴訟活動を行うほか、企業法務や国際取引、知的財産権の分野など幅広く活躍します。 「法曹三者(弁護士・裁判官・検察官)」のひとつとして、司法制度を支える専門職です。
弁護士は独立開業して個人の依頼に応じるだけでなく、企業内弁護士(インハウスロイヤー)として社内の法務部門で働く人も増えています。また国際取引やIT・AI分野の新しい法的課題に対応するケースもあり、従来の訴訟代理にとどまらない幅広い活躍が期待されています。人権擁護や社会正義の実現という使命を担う点でも重要な役割を果たしており、司法制度の根幹を支える資格として高い社会的信頼を持っています。
弁護士(司法試験)の受験概要
| 根拠法令 | 弁護士法/司法試験法 |
|---|---|
| 所管官庁 | 法務省 |
| 資格区分 | 国家資格(法律系の最難関) |
| 受験資格 |
法科大学院修了者、または司法試験予備試験の合格者。 ※予備試験は「学歴不問」で受験可能。 |
| 試験方式 |
● 短答式(マーク式) ● 論文式(民法・刑法・憲法など) ● 選択科目(労働法・倒産法・知財法など) ※予備試験も同様に短答・論文・口述の構成。 |
| 試験科目 |
・憲法 ・民法 ・刑法 ・商法 ・民事訴訟法 ・刑事訴訟法 ・公法系科目(行政法) ・選択科目(労働・環境・知財など) |
| 合格率 |
● 司法試験:約30〜40%(法科大学院修了者・予備試験合格者 計) ● 予備試験:論文以降は約3〜5%程度(年度により変動) |
| 資格登録 |
司法修習(約1年間)を修了し、 二回試験に合格後、日本弁護士連合会に登録。 |
弁護士(司法試験)Q&A
- Q1. 法学部じゃなくても弁護士になれますか?
-
もちろん可能です。
法科大学院は他学部の方も幅広く受け入れていますし、
予備試験であれば学歴の制限もありません。
途中から興味が湧いた方でも十分に挑戦できる道です。 - Q2. 予備試験と法科大学院、どちらが良いですか?
-
どちらにも良さがあります。
予備試験は受験費用を抑えられますが、合格までの競争は厳しめです。
法科大学院は体系的に学べるため、理解の土台が積みやすい点が魅力です。
自分の生活スタイルや学び方で選ぶ方が多い印象です。 - Q3. 勉強時間はどのくらい必要ですか?
-
個人差はありますが、数千時間規模といわれることが多いです。
ただ、一気にこなすというより、日々の積み上げで力がついていきます。
少しずつでも継続した勉強が、結果的に大きく前に進みます。 - Q4. 論文試験が難しいと聞きます。
-
最初は書き方のイメージが掴みにくいのですが、
事例の型を知ると、少しずつ書けるようになります。
過去問を丁寧に確認しながら、徐々に慣れていく受験生が多いです。 - Q5. 合格後の働き方にはどんな種類がありますか?
-
事務所勤務、企業内弁護士(インハウス)、公務員など選択肢は幅広いです。
関わる分野も、民事・刑事・企業法務・家事事件など多岐にわたります。
自分の興味に合わせて、長くキャリアを育てていける職種です。
弁護士が必要な職業/あると有利な職業
必ず必要な職業
- 弁護士:業務を行うために必須
公式情報/出典
- 法務省「司法試験制度概要」
- 法務省「司法試験結果(令和5年度)」
難易度: ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (難易度5)
※難易度は合格率・必要学習時間・修習過程をもとに当サイト独自に評価しています。