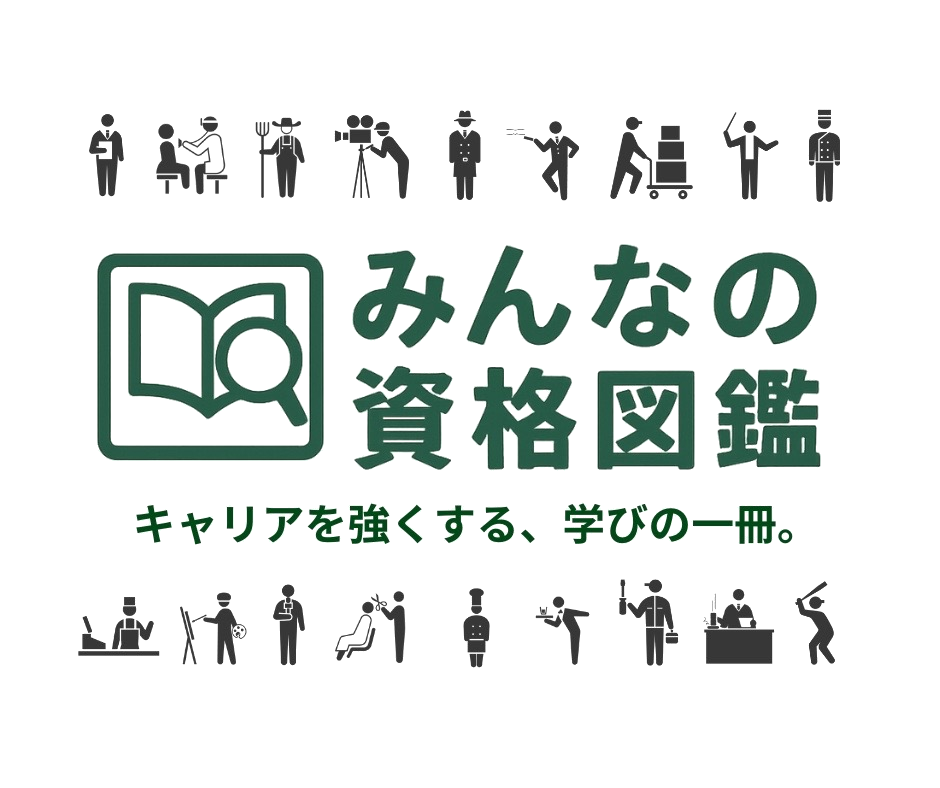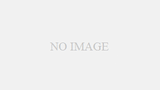地域伝統芸能等通訳案内士(ちいきでんとうげいのうとうつうやくあんないし)とは?
地域伝統芸能等通訳案内士は、特定地域の「伝統芸能・祭礼・民俗芸能・工芸・食文化」などに焦点を当て、訪日客や在住外国人に対して外国語で専門的に案内・解説を行う公的資格です。全国通訳案内士が全国を網羅する汎用ガイド資格であるのに対し、本資格は都道府県・文化関連機関の養成スキームを軸に、地域文化資源に特化した高度な解説力と現場運営力(動線・安全・鑑賞マナーの管理など)を身につける点に特徴があります。
対象となる「地域伝統芸能等」は、能・狂言・歌舞伎・文楽・雅楽のような古典芸能から、郷土芸能(神楽、祭囃子、獅子舞、念仏踊り)、工芸(漆・染織・陶磁)、食文化(発酵文化、郷土料理)まで幅広く、自治体や文化振興団体が定めるカリキュラムに沿って学修します。単なる逐次通訳ではなく、ストーリー構成、歴史的背景、演目の見どころ、演者・担い手への敬意や撮影・拝観ルールの伝達など、文化資源を「誤解なく・魅力的に」伝える力が求められます。
また、地域の祭礼や公演は屋外・夜間・混雑環境で行われることも多く、観客誘導や安全配慮、悪天候時の代替提案、バリアフリー対応など「現場運用」の判断力も重要です。観光消費の高付加価値化(体験・鑑賞・学び)を担う人材として、地域DMOや観光事業者、文化施設と連携しながら活躍の場が広がっています。
地域伝統芸能等通訳案内士を取るために必要なこと・取得概要
| 根拠法令 | 通訳案内士法/各都道府県の要綱・実施要領(文化観光振興の枠組み内で運用) |
|---|---|
| 所管 | 都道府県(観光庁・文化庁の指導・連携のもとで運用) |
| 受講・認定要件 | 18歳以上。所定の「地域伝統芸能等」カリキュラム(文化史・演目理解・鑑賞マナー・安全対応・接遇・多言語解説法など)を修了し、語学要件(英語ほか)と口述・実地評価に合格すること。 |
| 評価方法 | 筆記(基礎知識)+口述(解説ロールプレイ)+実地評価(会場での案内・安全配慮)。自治体により構成・比重は異なる。 |
| 資格取得までの流れ | 自治体・文化団体が実施する「地域伝統芸能等通訳案内」養成講座へ申込 講義・現地研修・演目鑑賞を修了(ガイド台本づくり・用語集作成などを含む) 口述・実地評価に合格し、都道府県へ登録申請 「地域伝統芸能等通訳案内士」証の交付・登録 |
| 活動範囲 | 登録自治体が定める地域・対象分野内での有償案内が可能(他地域での活動は再登録・相互承認が必要な場合あり) |
| 更新 | 自治体により概ね3〜5年ごとの更新・フォローアップ研修受講を義務化 |
留意点:制度は自治体裁量が大きく、対象分野・語学要件・評価方法・更新要件は地域ごとに異なります。記事化の際は各自治体の最新実施要領に合わせて細部を調整してください。
地域伝統芸能等通訳案内士が必要な職業/あると有利な職業
必ず必要な職業
あると有利な職業
公式情報/出典
- 観光庁/文化庁 公表資料(地域通訳案内・文化観光推進)
- 各都道府県 観光課・文化振興課 実施要領