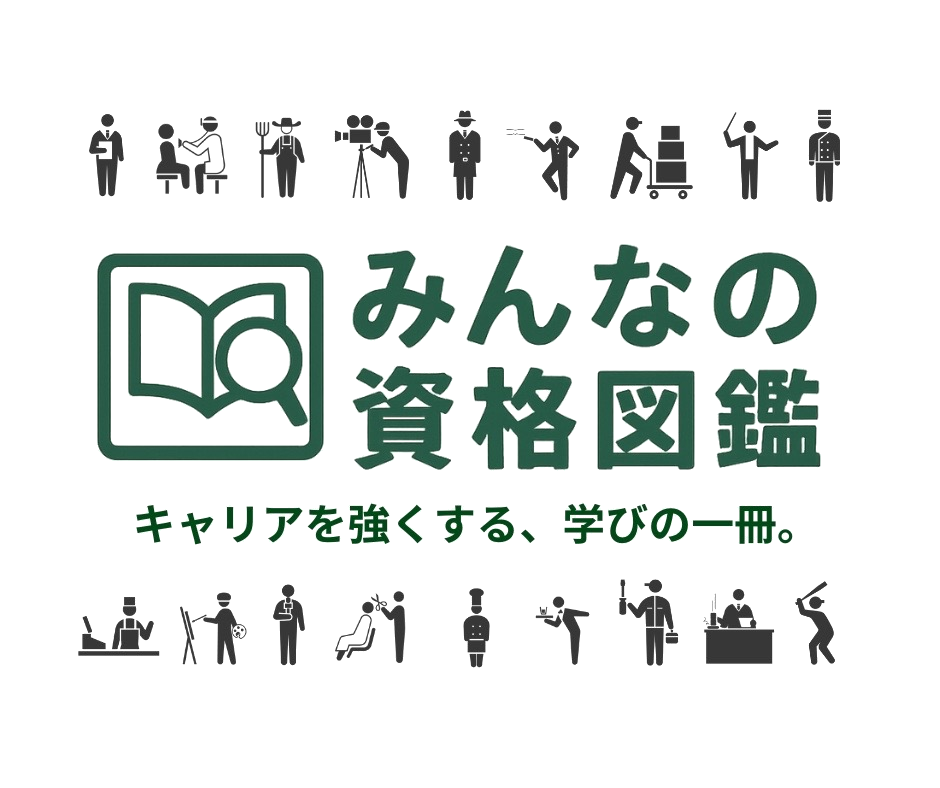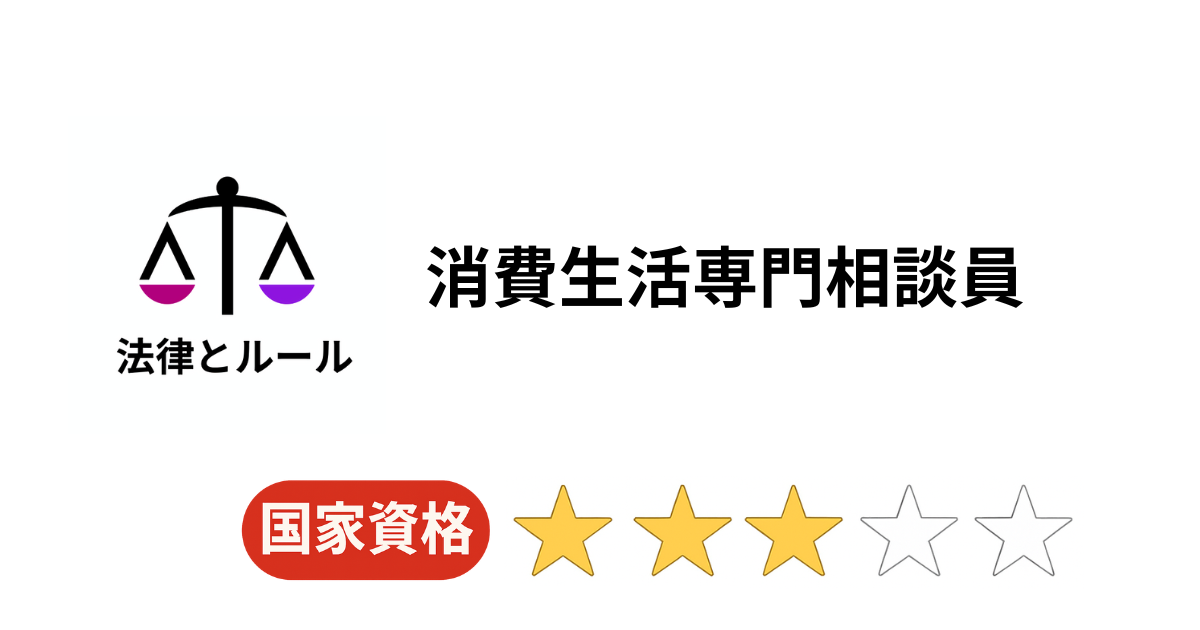法律とルールを守る仕事
消費生活専門相談員(しょうひせいかつせんもんそうだんいん)とは?
消費生活専門相談員は、消費者庁が所管する国家資格で、消費者からの相談を受け、問題解決に向けた助言やあっせんを行う専門職です。 消費生活センターや自治体の消費生活相談窓口で働くために必須とされ、消費者トラブルの予防や被害救済の最前線で活躍します。 2016年に創設された比較的新しい制度で、「消費生活相談員資格試験」に合格すると国家資格とともに「消費生活専門相談員資格(5年更新)」が付与されます。
近年はインターネット通販やSNSを通じた新しい消費者トラブルも増加しており、相談員には最新の知識や柔軟な対応力が求められます。地域の消費者を守る「生活のセーフティネット」として、今後さらに需要が高まる資格です。
- 資格の種類: 国家資格
- 分野カテゴリ: 公務員・安全
- 想定学習時間: 約300〜400時間
- 対象者: 消費者問題に関心のある社会人、地方自治体で勤務希望の人など
消費生活専門相談員を取るために必要なこと・取得概要
| 根拠法令 | 消費者安全法/消費生活センター設置条例(都道府県・市町村による運用) |
|---|---|
| 所管官庁 | 消費者庁・都道府県/市町村(地方自治体の管轄のもとで運用) |
| 受験資格 |
年齢・学歴不問。原則として実務経験は不要。 ただし、消費者行政・法律・生活経済などの知識を持つ人や関連講座を受講している人が有利。 |
| 試験方式 |
筆記試験(マークシート形式)+口述試験(面接形式)。 筆記は全国7会場で実施され、合格者に対して口述試験が行われる。 |
| 試験内容 |
生活経済・法律(消費者契約法、特定商取引法、景品表示法など)・行政制度・心理学・相談技法・事例分析。 実務現場での相談対応力を総合的に評価。 |
| 合格率 |
約25〜30%前後(年度により変動)。 受験者は毎年2,000〜3,000名程度で、合格者は600〜800名程度。 |
| 資格取得までの流れ | 指定講座(通信・通学)または独学で学習 → 年1回(11月頃)の国家試験に出願 → 筆記・口述試験 → 合格 → 登録講習を受講 → 各自治体で相談員として登録・勤務。 |
| 活動範囲 |
各都道府県・市町村の「消費生活センター」や「消費生活相談窓口」で勤務。 消費者被害の相談対応、トラブル解決の助言、行政への報告・調査などを行う。 |
| 更新制度 |
5年ごとの更新制。 指定のフォローアップ研修を受講し、最新の法改正や相談事例を学ぶことが義務づけられている。 |
| 留意点 |
自治体によって任用条件や募集頻度が異なるため、試験合格後すぐに採用されるとは限らない。 公務員(会計年度任用職員)として勤務するケースが多い。 |
消費生活専門相談員に関するよくある質問(Q&A)
- Q1. 消費生活専門相談員と消費生活相談員の違いは?
-
「消費生活専門相談員」は国家資格で、全国統一試験に合格した人が名乗れます。
一方、「消費生活相談員」は各自治体が任用する相談職で、資格を持たない人も配置される場合があります。 - Q2. 試験勉強は独学でも大丈夫?
-
独学でも可能ですが、出題範囲が広いため通信講座で体系的に学ぶ人が多いです。
過去問演習と法改正対策が合格のポイントです。 - Q3. 就職先はどんなところですか?
-
主に自治体の消費生活センターや役所の相談窓口で働きます。
会計年度任用職員としての採用が多く、地域住民の相談対応や講習会などの啓発活動を担当します。 - Q4. 年齢制限はありますか?
-
年齢制限はありません。社会経験が豊富な人ほど相談現場で評価される傾向にあります。
定年後に取得して地域貢献に活かす人も多いです。 - Q5. どんな人がこの仕事に向いていますか?
-
人の話を丁寧に聞ける傾聴力と、冷静に法的判断を下せる論理力の両方が求められます。
「困っている人を助けたい」という気持ちがある人に特に向いています。
消費生活専門相談員が必要な職業/あると有利な職業
必ず必要な職業
- 消費生活センタースタッフ:自治体や消費生活センターでの相談員業務に必須
あると有利な職業
- 公務員:地方自治体の生活安全課や消費者行政部門で採用に有利
公式情報/出典
- 国民生活センター「受験要項(2025年度)」
- 国民生活センター「2024年度 試験結果」
- 国民生活センター「資格制度Q&A」
難易度: ⭐️⭐️⭐️ (難易度3)
※難易度は合格率・学習時間・試験範囲をもとに当サイト独自に評価しています。